長野県のふるさとの味「おやき」。
野沢菜・かぼちゃ・なす・切干大根などの具材を小麦粉などで包んだもの。
おまんじゅうのような、パンのような、おやつのような、こころ安らぐ懐かしい味。
おやきの由来や、魅力、ソウルフードである理由、かんたんレシピをまとめました。

好きなものを具材にできる

おやきは簡単につくれる
- だれも食べない余りものがある
- 野菜の菜っ葉をよく腐らせる
- 少ない材料で1品つくりたい
- 残り物を処分したい
- 野菜の皮を捨てるのがもったいない
- 最小限の材料で作りたい
- おやつ・主食兼用で作りたい
- 冷凍保存可能なおやつを作りたい
- アレンジ自由なレシピが知りたい
- すぐ作れる
- 野菜の皮で一品つくりたい
- おやきの魅力
- おやきのおすすめポイント
- おやきの作り方
- アレンジ自由な簡単レシピ
長野県民のソウルフード「おやき」

長野県に、古くからある郷土料理「おやき」の発祥や由来、作り方をみていきましょう。

おやきの発祥
上水内郡西山地域が発祥といわれており、その歴史は古く、小川村の縄文遺跡からは雑穀の粉を練って焼いた跡が発見されている。
農林水産省ホームページ【うちの郷土料理】
おやきがソウルフードである理由
おやきが名物になった理由は、稲作が難しかったからです。
長野県の北部は、稲作をするの条件を満たしていませんでした。
稲作に必要な条件
- 水が豊か
- 広くて平らな土地
- 水はけが良い土
- 昼夜の温度差が大きい
長野県の地理の特徴
- 山間地である
- 急傾斜地
- 寒冷地
- 降水量が少ない
山間部に住む人々は、米の代わりとして小麦・蕎麦を栽培し、主食としました。
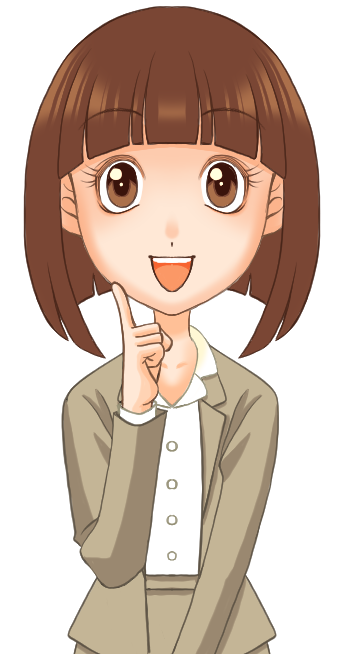
稲のかわりに小麦粉を栽培していたのね

灰焼きおやき 昔の家庭には囲炉裏がありました。 囲炉裏に掛けた焙烙(ほうろく)鍋でおやきを蒸し焼きにして食べていたたそうです。これを一般に「灰焼きおやき」といいます。
おやきの作り方
そば粉や小麦粉を混ぜたものに水またはお湯を加え、こねて生地にする。
生地の中に、季節の野菜やあんこなどのを入れて焼きあげる。
おやきの魅力
栄養豊富で、ヘルシー
- 野菜をたっぷり入れて栄養食・ダイエット食に
- 栄養のある野菜の皮を具にできる
- おやつにも、食事にもなる
- 栄養バランスがいい
- 夜食で食べたくなるサイズ感
手づかみで食べられる手軽さ
- 手づかみで食べられる
- サンドイッチ感覚で持ち歩きできる
- 手ごろな大きさ
- 手が汚れにくい
アレンジ無限大
- 具材は自由
- 残り物を具材に(カレー・シチュー・野菜炒め)
- おやつでも食事でも食べられる
- 緑茶・抹茶・黒ゴマを練りこんで生地を鮮やかに
冷凍保存可能
電子レンジでチンして食べたい時に食べられます。
冷凍しても、おいしさは変わらないのが魅力。
おやきを作ろう!簡単レシピ

用意するもの
器具
ボウル、フライパン
具材
残り物(今回は、腐りかけの菜っ葉を塩コショウで炒めたものです)
具材は野菜の皮や、冷蔵庫の残り物でもOK。
生地
小麦粉(薄力粉 50g・強力粉 50g)
塩 ひとつまみ
お湯 75g
熱湯でこねる理由は、糊のような粘りがでてモチモチ食感になるからです。
おやつとして食べたいなら、生地に砂糖やはちみつを混ぜてみましょう。
皮の配合は、薄力粉だけでもOK。ふくらし粉を入れてふんわり食感も試してみて。

アレンジ無限大
手順
- 小麦粉と塩をボウルに入れる
- 水またはお湯をボウルにそそぐ
- 耳たぶくらいの硬さまでこねる(5分~10分くらい)
- 常温で1時間くらい置く
- 生地を4等分して、具材を包む
- フライパンで焦げ目がつくまで焼く
- 水を加えて蒸し焼きする(2分くらい)
- 完成
完成したおやき

きれいに焼けました!具もびっしりで食べ応えあります。
手作りは、自分の好きな具材を好きなだけ入れられる幸せがありますね!
蒸し焼き・揚げ焼き・トースターで焼いたり。いろんな食感や具材を楽しみましょう!
ぜひみなさまもチャレンジしてみてください♡
まとめ
おやきは、信州を代表する郷土料理
おやきの発祥は、上水内郡西山地域
米が作れない地域だったので、小麦や蕎麦を原料とした「おやき」が広まった
あん(=具材)には野菜・山菜を入れるのが一般的
生地は小麦粉があれば簡単に作れる
好きな具材を入れて、オリジナルのおやきを作ろう

最後までお読みいただきありがとうございました。


